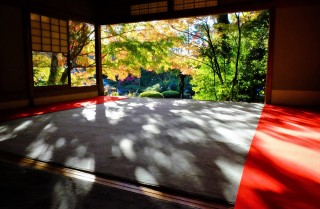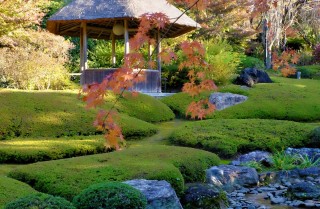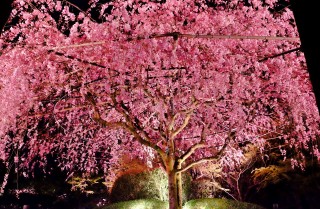_坐禅とは
お釈迦様の心(悟りの心)を坐禅で直接体験することを目指すのが禅宗です。坐禅を続けることで、自分の心の持つ清浄心に気づき、「無生心(むしょうしん)」「無住心(むじゅうしん)」が得られるとされています。
_坐禅の効用
本来、坐禅は自分の役に立つからとか利益が得られるからとか目的のためにするものではありません。しかし、坐禅をすることで、結果としていろいろな功徳が生まれてくるのも事実です。坐禅によって体、呼吸、心を整えることは、心を落ち着かせ体を健康にさせます。
_服装
体を締め付けないもの。上着を脱いだり、ネクタイやズボンのベルトを外します。女性は短いスカートは避けます。また、極端に薄着になったり、ぶくぶく着込んでもいけません。
_足の組み方
両足を組む結跏趺坐(けっかふざ)、片足だけ組むのを半結跏趺坐(はんけっかふざ)の二通りがあります。結跏趺坐が難しい人は半結跏趺坐をするとよいでしょう。
結跏趺坐はもっとも安定したもので、お釈迦様が菩提樹の下で悟りを開いたときの坐り方です。
結跏趺坐のやり方は左ももの上に右足を乗せ、右かかとを腹に近づける。次に右ももの上に左足を乗せる。一方、左足のみを右ももに乗せるのが半結跏趺坐である。いずれも両足と尻との3点でつり合いよく座ります。
_手の組み方
手の組み方は印相と呼びます。一般的なのが法界定印(ほっかじょういん)と呼ばれるもので、大日如来の三昧の境地を示すもので、お釈迦様が悟りを開いたときの印相でもあります。
組んだ足の上に右手のひらを上にして載せます。左手も同じように手のひらを上に向けて右手に重ねます。両手の親指を紙一枚入るぐらいあけて、お互いを支えるようにします。
もうひとつ、結び手と呼ぶ組み方があります。右手の親指と人差し指で円をつくり、その中に左手の親指を入れます。そして、左手全体で右手をおおうようにします。白隠流と伝えられています。初心者にはこちらが向いています。